みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
最近読んだ書籍、及び、最近に出会い話した人たちとの対話から、私は子供の自立の在り方をなんともなく考えるようになりました。
そう。
少し前まで、親の子育てのゴールは“子供を経済的に自立をさせること”に他なりませんでした。語弊があるかもしれないけれど、概ねそう言えると思ってる。そしてその“少し前”というのも本当に少しだけ以前の話であり、今40代の私の世代でもそう育てられたであろうと感じています。
すなわち初等教育の学校から良い成績を取り、良い高等教育機関に入り、良い会社に就職して良い配偶者と出会い…果てなく続きます、そうして不自由のない(ように見える)生活を送りその子供にも存分に学資を出してやれるように、そうなるようにと育てられてきたのが我々です。
私の母は、よく私にこう言いました。
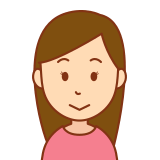
女の子であっても、自分の食い扶持は自分で得なさい。配偶者とは対等に、頼り切るようなことはいけない、自分と自分の子供の食い扶持は自分の力で得るように、自分の足で立てるようにありなさい。
私の母は、私の自立をこう説きました。母の世代では、『女の子には高いレベルの教育は不要である』と言われてきたこともあるでしょう。大学ではなくとも専門学校や短大に行くなどした女性もいたとは聞きますが、しかし卒業後は親の近くに戻って結婚して家に入ることが当たり前という空気感、たった50年前の地方都市ではまだまだだったそうのです。地方都市の一部では今なおそうかもしれません。
1980年生まれの私くらいの世代では、女子の高等教育への門戸がだんだんと当たり前に開かれ始めた世代ですから、母は私が進学することを、父や祖父母が貶める中でも心から応援してくれました。おかげで今の私があります。
だから私も、私の息子に対してはずっとそう思ってきました。
『良い学校に進学して、そこでしか得られない良い仲間と巡り合って、人から求められ必要とされる仕事に就いて、経済的に不自由なく好きなように幸せを求めて生きてほしい』と。
私はこれまで、暗に明にも、息子にそれを求め続けてきていたことを知りました。
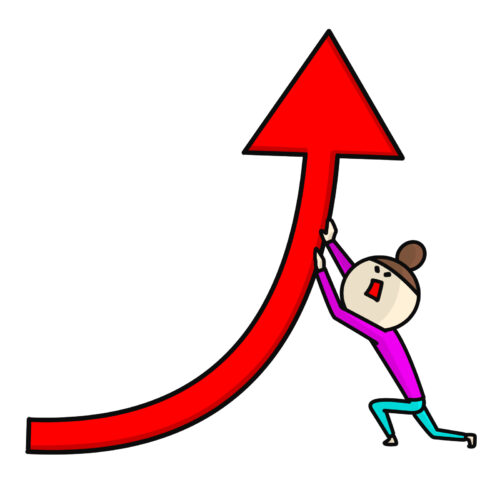
しかし私は、今の息子の様子を観察すればするほどに、『息子は、そんな生き方を求めていない』と、実感としてそう感じるようになってきたことが私の大きな変化です。
これまで私は、私のこんな思想を息子が理解してくれない!と、歯痒く感じてばかりでした。
だけど今の私はなんとなくでも感じてきました。
息子はそれを求めていない、と。
こんな私の心の変化は、概ね何人かの対話の中で出てくる価値観と合致していて、これまでの子育てのゴールであった“子供の経済的な自立”というのは、社会の中で、特に今の不登校児童増加を受けて、全体的に変遷しつつあるのではないかと感じます。
実際に、
『やりたくないことはやりたくない』
『人を蹴落としてまで勝ち上がりたくない』
今の子達の中には少なからず、そのような行動原理を示す子がいます。昭和世代の大人から見れば無欲にも、ひいては無気力にさえ見えてしまうから歯痒いですが、今の社会がそういう子供を育成したのかもしれません。そんなことを感じます。
『そんなんじゃ、社会に出てから通用しないぞ!』は昭和世代のキメ台詞ですが、何よりも、すでに学校は社会で我慢する練習の場ではなくなりました。我慢して学校、我慢して仕事、そんな人生を送りたい人はもういない、真っ平ごめんだと、そういうことに子供が気づき始めたのかもしれません。
同時に、たとえ子供時代に時間を費やし東大や京大に入っても出身大学のブランドだけで食っていけるような時代ではとうになし、そういうことに価値を見出せなくなった子供が増えたのだろうとも言えそうです。
少し前のことで記録がすぐに出てきませんが、私は数年前に参加した、成人ギフテッドの方々の数名がオンラインで講演をなさる講演会でとても印象的だったご発言を覚えています。
確かどこかのお母様が、子供が自立できるかどうか心配だというご質問をなさったことへの返答に、この方はこのように回答をされました。
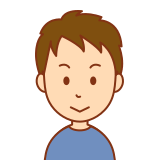
経済的に自分が自立できないのであれば、経済的に自立しているパートナーを得れば良いのです。全ての面で必ずしも自分で自立していないといけないわけではありません。(←文脈は異なるかもしれませんが、こんな内容でした)
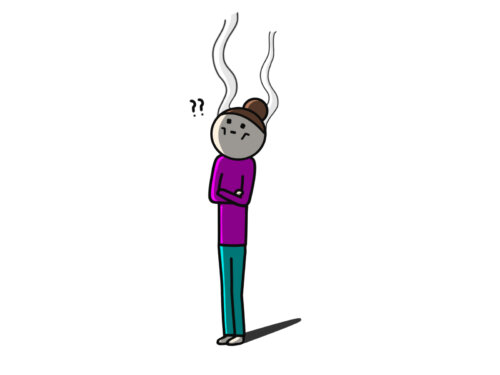
この時、当初は、私は違和感を感じたものです。類は友を呼ぶとはよく言ったもので、経済的に自立していない人に経済的に自立しているパートナーが得られるわけがないじゃないかと謎の反発心を私は強く感じました。(←これぞ昭和の考え方です)
だけどもこの時の回答が、今になってなんだかじわじわ、私に染み込んでくるようで、だんだんと理解できるような気がしてくるから不思議です。
本当に、じわじわとです。じわじわと染み入ってくるように考えさせられています。
苦手なことややりたくないことに立ち向かい、抑うつや精神的な重荷を抱えてしまう時代はもう終わりなのかもしれません。
人は誰にも得手不得手があることを前提として、“お互い様”の精神で回る社会は生きやすい。
単に経済的な自立だけを目指すのではなく、自身の健康維持・生活力を基盤とし、自分らしく生きていればそれで巡り合う仲間もいます。行き当たりばったりでも良いじゃない、それで飢えるならまた何かを考えていけばいいのだからと、最近の私はなんとなく、そんな考えを取り入れるようになりました。
ーーー書籍紹介ーーー
不登校という現象を冷静に見る語り口が美しい書籍でした。不登校→どう支援するかとか、そんなうわべのことでは全くなくて、歴史を踏まえて意味や意義といった本質に切り込んでいて、俯瞰的に不登校を考えさせてもらえました。

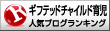

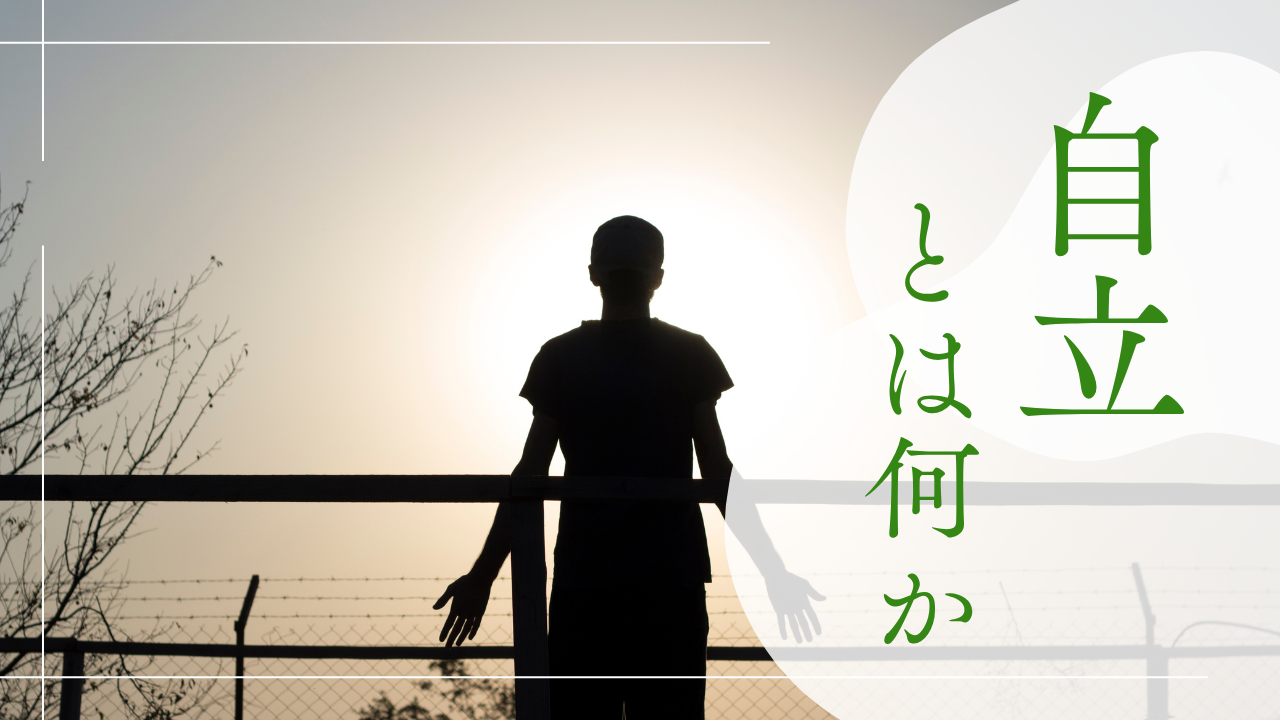





コメント
はじめまして。高IQの不登校児11歳男子をもつ母です。息子の中学の進路についてヒントを探す中で、こちらのブログに出会いました。
上の子は高1ですが、今思えばASD傾向で幼い頃から癇癪と0か100かの反応に苦労した経験があり、今は社会性がついて少し接しやすくなったと思える状況です。
Naomiさんの記事をいくつか拝読して、そうなんだよなぁ、と心底共感することが多く、同じ思いを抱えながら、目の前の子供の様子を受け入れながら過ごしていらっしゃるご様子に励まされ救われる思いでした。
こうした発信をしていただいて本当にありがとうございます、とお伝えしたくてコメントさせていただきました。
不登校のお子さんは身近にも少なくないですが、要因はさまざまで、いわゆる浮きこぼれでの学校のつらさはなかなか共有する出会いもなく、なんとなくギフテッドという言葉や高IQの言葉のイメージで生きづらさを理解してもらいにくいことも実感して、親が自分の体験とのギャップから受け入れに葛藤したり、情報が少なかったりでしたので、Naomiさんのように私も経験を発信できたらだれかにつながるだろうかと考えたりもします。
これから過去の記事もじっくり読ませていただきますね。長文失礼しました。
コメントありがとうございます。私個人の経験からの拙い発信ですが、共感やさらなる発信へと向くお気持ちが心強く感じています。
どんな形であっても、親の「子供に幸せになってほしい」という気持ちは何よりも強いものです。受け入れに葛藤するのも仕方なし、親だって完璧ではありませんから。だけど親がまずは「我が子はこういう子だ」と確たる心で受け入れてこそ、また見えてくるものがあるんじゃないかなと自分に期待しているところです。未熟な私はまさに一歩ずつです。