みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
少し前のことですが、私は知人からの勧めを受けてこちらの書籍を拝読しました。今夏に出版されたばかりの新しい書籍で、何気なく手に取ったのですが、頭を打たれたようなとにかく強い衝撃を受けましたので記録しようと思います。
感想を一言で申し上げれば、「すごい本だった…」という感じでしょうか。
こちらの書籍は“地方女子”というタイトルが付けられておりますが、富山県の出版社から出版された、富山県という土地で育った/人生の部分を過ごした女性たちに100%の焦点が当てられ書かれた書籍です。
富山弁が随所に登場しますので、富山弁話者の私にはリアルで痛いほど読みやすいです(富山弁非話者には難解かもしれませんが意味は伝わると思うよ、笑)。おそらくこの内容も、富山県に馴染みのある方にとっては決して他人事と思えないものでしょう。
富山県のみならず、地方都市、または都市部に距離的には近くとも不自由さの残る全ての土地に育つ女性にぐさっと刺さる内容だろうと思います。
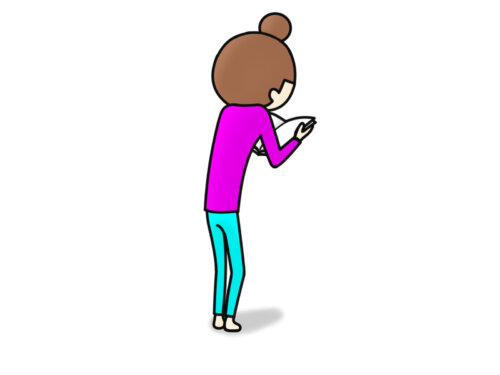
地方都市の女性といえば、近年ではニュース等でよく取り上げられるのは“若年女性の都市部への流出が止まらない”という現象です。



そらそうやろな、当たり前やし当然のことだわ。
出産を担う年齢層の女性が転出過多の地方自治体は早晩滅びの一途をたどりますよということですよね。自治体にとっては深刻なのかどうかは知らんけど、かつて娘時代に地方都市を出た当事者でもある私はこれは『当たり前』としか思いません。
実際に、私は故郷である地方都市から都市部へと出て行った女性の一人です。18歳だった私はあの時、強く心でこう思っておりました。
『こんなところ、二度と戻ってたまるか!!』と。
時代柄、無支援で育った高IQ者で特性の強い父の仕事は安定しておらず、私が育った家は決して裕福ではありませんでした。私は大学進学を機に、満額の奨学金を借り入れて、今後一切の援助も不要だと言い切って(それでも私の母が時々幾らかの仕送りをしてくれ、学費の半分を担ってくれたことは本当にありがたいことでした)、私は県外の、いわゆる旧帝大である国立大学の理系学部に進みました。それでも親戚からは「女が大学なんて」「親を見捨てる人でなし」と嫌ほど嫌味を浴びながら。
18歳で、周囲に説明可能な程度には名目の立つ大学進学を掴み取ることは、あの当時の私にとっては家を出るための唯一の「正当な手段」だったと言っても全く過言ではありません。
地方都市には独特の謎の風土が蔓延ります。女の子への言われのない無根拠な抑圧という風土です。(もちろん家庭によりますことを申し添えます)
私はそれが苦しくて、苦しくて、いつもすごく嫌でした。
だから私は家から出たい一心で受験勉強し、結果として掴んだ進路は晴れやかで、清々した気持ちでいっぱいでした。
これを私は今までずっと愚かにも、「これは私が自らの努力で勝ち取った未来である」と思い込んでいたのです。
しかし私は本書を読み、そうではなかったと気付かされました。それが私が受けた衝撃です。
私には、ずっと想像が欠けていました。地方都市でそんな抑圧を受け続けたのは私の世代だけではないことを。本書の中では、そのことが多様な世代の女性へのインタビューを通して綴られました。
特に、私の母親世代の葛藤と苦しみが顕著でした。
私の母親世代はおそらく、“嫁”という立場を強いられた最後の世代。語弊があってはいけませんので、つまり、今“妻”であり“母”である我々女性は、地方都市の家父長制度の中における“嫁”とは全く次元が異なるレベルでの尊重を受けているという意味合いです。
そんな私の母親世代の胸中では、
『娘には、どうか自由を』
そのことが、密かながらも最大の願いだったのだろうことがありありと綴られておりました。読み進めるうちに、私はところどころで天井を仰ぎ、深く考えさせられました。
そうか。
18歳だった私が「二度と戻るか!」と憤りながらも脱出を果たすことができたことは、すなわち私の大学進学は、私の独力だけで叶えられたものでは決してなかったことを、私はそれをこの年齢になりようやく知るに至ったので慄いたのです。
今の私の自由があるのは、“私の母”という犠牲の上にほんの少しだけ開いたような隙間から、たまたまにゅるんと出れただけ。まさに本書で書かれる通り、娘であった私の自由は、母と娘の二世代ががりのまさに執念の達成の結果に過ぎないことを知りました。私がにゅるんと滑り出たのは、その隙間をこじ開けるための先代の並々ならぬ思いがあってこそだった。それなのに、私は自分の努力だけを誇ってきた浅はかさを突きつけられて、恥じ入るばかりの思いです。
そんな私の母は苦労を重ね、いつの間にか老い、昨夏突然亡くなりました。私は母を顧みず、大切にしたり優しい言葉をかけることも振り返ることもしなかったことをも悔やみました。本当に大きな衝撃を与えられた書籍でした。本当に、自分が自分で恥ずかしいとしかいえません…。
一方で、地方都市の根深い謎の風土には深く頷かされるばかりでした。印象に残った部分はたくさんあるのですが、例えばこういう部分もそうですね(↓)
地方では少数派はひどく肩身が狭い思いをする。少しでも人と違う人を見ると、ねっとりした陰口を言わずにはいられない。そんな陰気なメンタリティは、もちろん私の中にも巣食っている。心に浮かぶ陰口は、いつもなぜか富山弁で聞こえてくる。
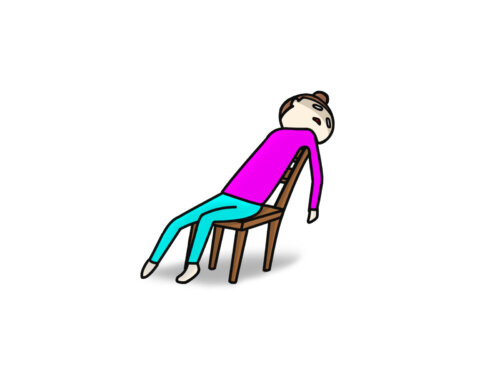
私はそのようなメンタリティは拭い去ったつもりです。少数派が肩身の狭い思いをしないといけない謎の風土は滅んで欲しいの。
心理学の本で読んだが、やたら陰口をいいたがる陰気な気質というのはいじめや虐待を受けた人に見られる傾向だそうだ。もしかして富山での生活は、知らず知らずのうちに自分を押し殺して我慢している。
「擬態するのは辛いですよ」
端々に見える、苦しさの連鎖、押し込めの連鎖。押し込める側の年配者や男性側にも怯えの心理が見て取れるところがすごく興味深く書かれていて、これぞまさに“風土”ってやつなんだろうなと思いました。
一方で、幸福な事例も多々書かれてありました。
その際の重要な要素としては、女の子の実家が有効なリソースとして機能していることが一つですね。妻方同居という幸福モデルもそうでしょう。また、一人でも生きていける、どこでも生きていけると思った時に戻ってくる先を感じられることもそうでしょう。
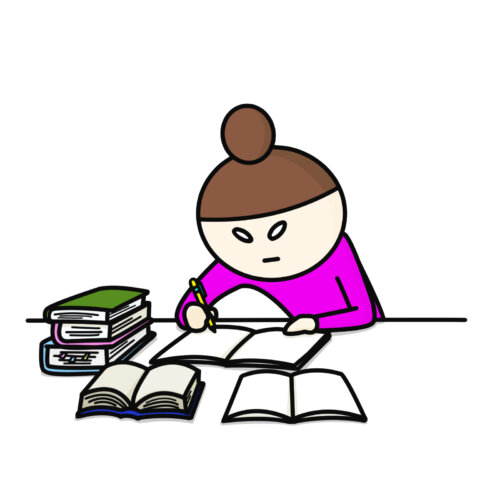
地方都市の中の女の子と、今の日本の中の高IQ者に、通じるものも感じられました。マイノリティの幸福モデルに一般化の可能性を感じられてとても勉強になりました。
また、少数派(地方都市に育つ女性)が、その土地を諦めただ去ることを選ぶのは、明確にその社会には構造的な欠陥があるからだともよく理解できる書籍でした。それは当事者の自己防衛のための行動ですから、地方都市から出ていく女性が悪いわけでも、責められたり気に病んだりする必要もないことだとも分かりますよね。もしかしたらそれはさらに、ノーベル賞を受賞するような日本人科学者の複数人もが日本を見限り外国籍を取得していることも同じことかもしれません。
ギフテッド児の不登校も、同じ構造なんだろうとよぎります。『こんなところ、二度と戻ってたまるか!!』って思うんだと思うんだよね。
もしマイノリティの心離れからの脱出や、真反対では意欲の冷却という実態を阻止しようと思うのならば、本書にも結ばれているように、社会側が価値と居場所を取り戻すことが先決であることに、私も非常に深い共感を感じています。
若い女性も、ほんの子供のギフテッド児も、決して当事者が悪いわけではありません。その認識を広く持ってもらえたならば、理解はまた進むのではないかと思うのですが、なかなかそこには至りません。何が壁になっているのでしょうか。
私に取っては自身の生き様を振り返り頭を打たれる、本当に衝撃的な書籍でした。
また、地方都市で生きる女性のお心が大変深くまで書かれていることも、素晴らしい書籍だったと感じます。このようなテーマを取り上げてくださり、出版に至るで力を尽くされた全ての方に感謝を感じたことと同時に、マイノリティへの議論が一層深まるためにも、小さなことからでも発信され続けることの重要性を実感した書籍でした。
ご関心のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。おすすめです。
ーーー書籍紹介ーーー

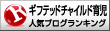




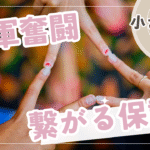

コメント