みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
しばらく更新が滞ってしまいました。ご心配をおかけした皆様、お気持ちを寄せてくださり本当にありがとうございます。
私たちは急激に季節が進んだ影響で、私の娘(現在小2)は風邪をきっかけとした体調不良、そして喘息の発作を頻発して起こしてしまい、しばらくは自宅待機の看病生活をすごしていました。
ええ、娘は季節の変わり目に、特に秋口には毎年のように喘息の発作を起こす子です。対策が必要ですが、なかなか発作を予測することは難しく、ついつい後手に回りがち。今回はちょっと酷かったので目が離せない状況でした。
その兄である息子もまた、幼い頃にはよく喘息の発作を起こしました。息子は娘よりも症状が重い子で、たびたび入院を繰り返すような時期もありましたが、成長に伴い発作は起きなくなりました。体は強くなるのですね。
この看病生活で、私はちょっと感じたことがありました。

なんだかさ、外に出ないと気持ちも弱っていってしまうのね。
ずっと家にこもっていると、だんだんと気力や意欲が減退していくような感覚を覚えました。
私は、どこへでも行き、誰とでも話すことが割と好きな方だと思うのですが、そういうことの一つ一つが億劫になってしまいました。
この10月には、東京で日本LD学会の学術総会が開かれました。ギフテッド児について議論されるセッションもあるというので、見に来ないかとお声がけもいただきましたが、結局それも行けないままとなりました。
えいやっ!と、行こうと思えば行けたのかもしれません。今思えば、残念です。それでも私の心はなぜだか全くわからないけど、自然と二の足を踏んでいたのです。

気力が湧いてこないんだよなぁ…
他にも、予定を忘れてすっぽかしてしまったり(歯科の受診とかね、申し訳ない)、メールの返信すらもなかなか心も体も向かない日々が続きました。
そして何より、心が弱くなってしまうと、普段なら何気なく受け流せるような声掛けもいちいち(私が勝手に)悪く解釈しすぎてしまうことや、当サイトに時々ある“搾取的な依頼”にもいちいち傷ついてしまうことがありました。
確かにさ、看病は気を張るし大変です。もともと忙しい日々の中で疲れていたかもしれないし、自分のペースも崩れました。それにしても、たった数週間の自宅待機の期間において、私の心はここまで弱ってしまうものなのかと驚きながら、それでも私は鬱々と、何もできないままでした。
これじゃいかん!と友人に話を聞いてもらう中で、ふと気がついたことがありました。
同じメカニズムによる意欲の減退は、不登校の子供にも十分起こり得るのではないだろうか。
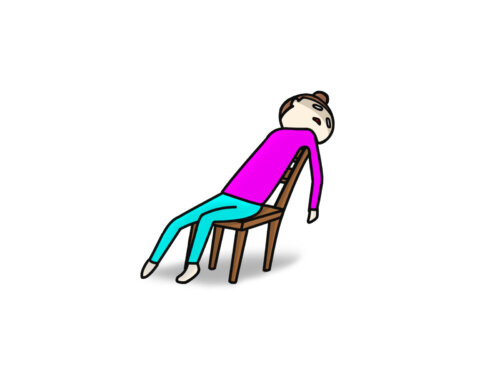
それは今の私の息子にも言えることです。
彼は私立中学校に編入はしたものの、だんだんと学校からは足が遠のき、今は再び完全不登校の状態です。少し涼しくなった今もなお彼は散歩にも出ようとしませんし、つまり用事もなく外に出ることを極度に“面倒くさがる”という状態で、息子の外界との繋がりは狭まる一方です。
そうかもしれない。
回遊魚のような、泳ぎ続けないと死んでしまうは流石に言い過ぎかもしれないけれど、人にもやはり同様の側面があるのだろうとも思います。
意欲が落ち込んでしまったり、例えば不登校の状態にあったとしても、それでもどこか外との繋がりを維持しようと努めることの重要性を改めて感じたように思いました。
子供だけじゃない、大人もそうよ。
発達に特性がある子を育てる親は、職業としての仕事を続けられない状態にも容易になり得ます。事実、かつて私自身もそうであり、息子のことで心が支配され過ぎてしまって研究職を続けられなくなりました。また、最近でも個別相談の機会の中で、もう仕事を続けられないかもしれないと嘆くお母様にもお会いしました。
大人にもどこかしらの『行き先がある』という状況が、心の塞ぎを防ぐための命綱になり得ます。
居場所の確保。
それがどんな場所でもいい。帰属意識を感じられる居場所がどうかあらんことを。
そのことは我々の、何よりの喫緊の課題なのだと、この機会に強く感じています。

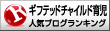

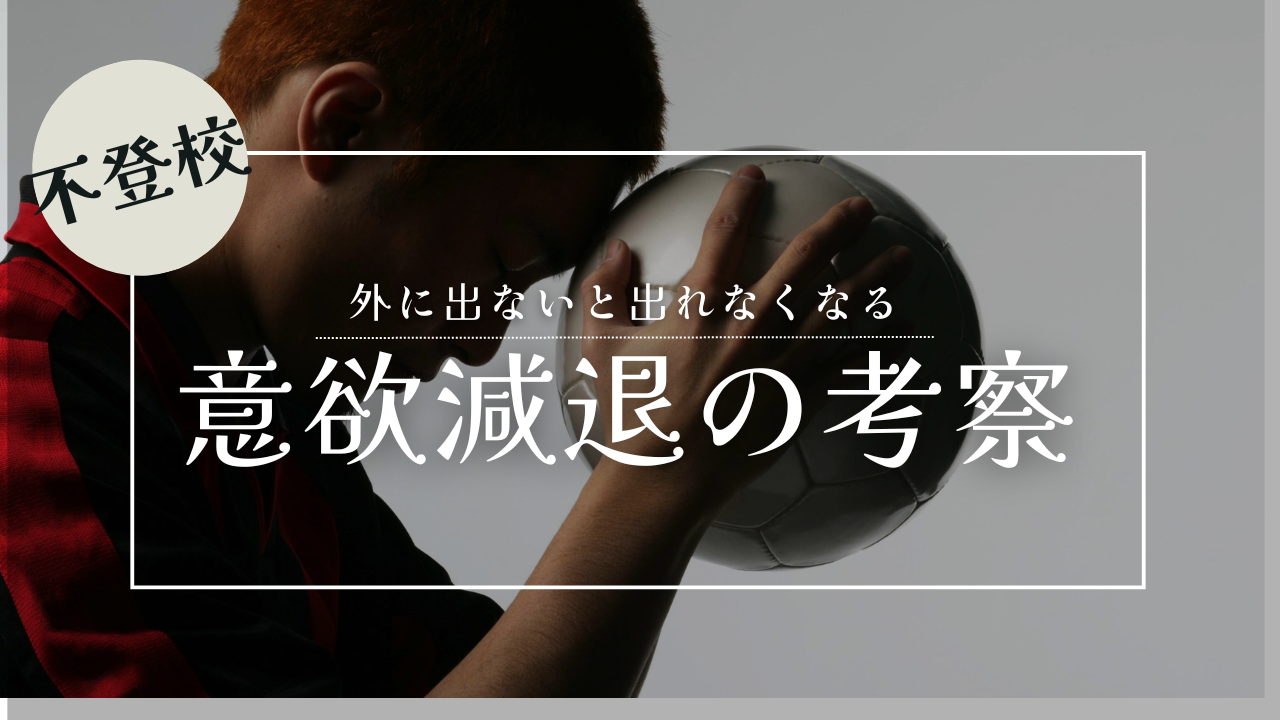


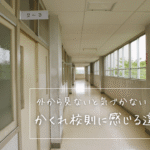
コメント