みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
秋も深まり、今日はもうすっかり寒いくらいですね。今日は私が高校教諭という仕事を通して考察中の、子供たちのそれぞれの賢さについて少しだけ触れておこうと思います。
高校生は、これがなかなか忙しい日々を過ごしています。
特に私がいまたまたま勤務している私立高校は、学業や進路指導に手厚いことが特徴です。在籍する高校生は、1年生から毎週のように校内小漢字テストを受け、半強制的に外部模試を毎月受け、放課後には習熟度や選択科目ごとに特別授業を受けてその課題提出と、その上でさらに部活動や友達づきあいもしている子達です。

君たち、毎日本当になんやかんやと忙しいねぇ〜。
と、休み時間にも時間を惜しみ漢字テストのプリントと睨めっこをしている子たちを見ると、こう口をついて出てしまうわけです。もちろんね、高校は進学先を自分で選べる場所であるのだから、その忙しさも自分の選択の結果です。粛々と受け入れなくてはなりません。

とはいえな、そんな「面倒見の良い学校」を選んで入ったのは君たちだ。どんなことにも楽しさを見つけて、大人をみんな踏み台にして、高く飛んでいきなされ。
基本的に育ちの良いとても素直な子が多いので、私が何かの授業の時にこんな(↑)ことを呟いた時にはいろんな反応がありました。

家が近かったら来ただけだけど、そう言われたらそうだな、仕方ない、笑。

僕はこの学校なら面倒見が良いって聞いて、塾に行かなくても勉強ができるから選んできた(←部活動もしっかりやりたい派)。

私は高校受験で第一志望に落ちちゃったからー。
そうかそうか、みんないろんな経験を経て、この学校に来たんやな。私もここに勤めることになったのは古い友人からの声掛けがあってたまたま来ただけだけではあるけど、せっかく一緒の時間を過ごすんだから楽しくやって行けることが一番だなと微笑ましく思いました。
そんな高校生らもこの時期は、もう少ししたら定期考査(期末試験)を控えています。
それは私の教員視点で眺めれば、私が彼ら彼女らの理科の授業を受け持ってもう半年以上がたちましたが、それぞれの子の成長だったり変化などが見えてくる、そんな時期でもあるのです。
総じて感じられるのは、『質問ができる子』ってやっぱり良いなって言うのが一つ。これはホンマにそうなのです。
基礎学習が良くできて、授業中もフンフンと頷きながら聞いていて、定期考査は上位の成績。そんな優等生のような子もいます。一言で言えば“学力が量的に高い子”です。
一方で、定期考査の成績はソコソコだけど、授業中にもその後にもノートを持って俯きながらやってきて、教壇で仕舞い支度をしている私に「ここが全く全然わからなかった」と率直に訴えてくる子もいます。言ってしまえば、“量的な学力はソコソコ”だけど、その余白を素直に周りに頼ることで埋めれる子。こういうタイプの子は、この時期には伸びてきたなと感じています。
何が良いって、授業の後に質問する子がひとり来ると、もうひとり、もうふたりと集まってきだすことです。そこで輪ができ、ネットワークが共有されます。こちらも人間でありますので、素直にやる気を出そうか出すまいかとしている子は可愛く見えるし、

あぁ、その問題はこの前に別の子もつまづいていたわ、その後その子は出来るようになったみたいだから呼んでくるよ、ソイツに説明させようぜ!
と、ちょっと質問しに来ることで出来るようになった人を紹介されてしまいます。さらに迂闊に理解したフリをしようものなら『だったら説明してみろよ』と周りから任されてしまい、しどろもどろでも説明し出す勇気もかなり偉いと思う。
そうやって、なんだかなんだで“素直に質問できる子”は理解度が上がり、定期考査の点数も一応はゆるやかな右肩上がりを示します。なるほど、これが伸びるという現象か!と、私はここ最近になり感じられたりしています。
優等生も良いと思うよ。家できっと自分なりに予習復習しているのだと思われます。定期考査の点数は、高いままで平行線、それもとても立派です。
一方で、伸びていく子の成長もまた面白いし、それは絶対に『大人に率直に聞ける』という能力により支えられていることを感じます。
私の感覚的なものではありますが、このような子の両者の“定期考査の点数”が逆転する日は、、、私はたぶん来ないだろうとは思います。良い具合まで追いつきそうになる日はくるかもしれませんが、明確な逆転は起こらないと思ってる。
そう。私は生来の頭の良さを発揮する高IQ児をたくさんみてきておりますが、やはり生まれながらの“学力の量的な高さ”というものはとても恵まれた資質です。ソコソコの学力の人がソコソコの努力だけでは決して追い越せるものではないと思うのも、ホントに率直な感覚で。
お分かりいただけると思いますが、もちろんね、どちらが良いとか悪いとか、優れているとか、そういう話では決してないの。自分なりに、自分なりのやり方で生き方を身につけていくということです。質問力は、今育むのに良い力だと思います。
そういうことがこの時期にできる子は、きっとその子らしい在り方で、周囲に恵まれ、幸せに生きていくだろうと思われるという具体事例の一つです。
さらに余談。この学校には私が受け持つクラスの中に、明確にギフテッドの特性を示す男の子が1人います(本人は知らないと思うし私も言わないけど、とても気にかけている子です)。
面白い事例がありました。私は以前の学内考査で、基本問題の中に1問だけ、頭を回して本質を見直さないと解けないような、そんな原点に立ち返るような問題をそっと出しました。

さて、何人くらいこの問題を解くかしら?
それを見事に、なんとも華麗に解いてきたのはそのクラス内で彼だけだったという事実が、私を改めて驚かせたのは最早言うまでもありません。優等生は解かない問いを、彼はスルッと解いてきた。さすがだな、と言うか、「やっぱりな」と思いました。
さらに面白いのが、その彼は“その問題しか”解かなかったということです。『時間配分をミスりました』とその子は言っていましたが、目が向いた問題に夢中になってしまったのでしょう。点数自体は低めでも、その答案は思考が見えて本当に美しいものでした。
彼のような人の知能は、いわば“質的に高い”のです。そう、質が違う、ベクトルの方向性が大多数とは違うがかなり大きい。
私は大学教員の経験もありますが、今もこれからも大学側が欲しいのはそんな知能の持ち主です。そんな子の存在も、もっともっと評価されていってほしいと私はずっと願っています。

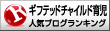






コメント