みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
今週8月26日(火)には、当サイトで不定期な定期的開催を設けている対面形式の情報交換会(:保護者及び当事者+時々何かの専門家を招聘します)の第9回目が無事に開催されました。
話が尽きず、今回ご参加いただいた皆様は知見も深く、お子様同士の世代も小学生高学年〜中学生と割と近かったこともあり、個々の様々なご経験をお話しいたくうちにありあれやこれやと盛り上がってしまって、無粋な私は写真の一枚さえ撮ることを忘れてしまうという…😱雰囲気をお伝えすることさえ難しくなってしまいましたが、良い会だったと思います。
ご参加いただいた皆様からフィードバックでいただいた個別意見から見えてきたのは、
やはり“子供の特性を話し合える理解者の繋がりの少なさ”だったり、“事例共有”、そして“今後の見通しの持ちづらさ”が、このような子を育てる課題であると私自身は感じました。
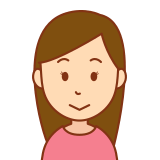
これまでスクールカウンセラーの先生以外に、ギフテッドとしての娘の困り事を話した事がなかったので皆さんとお話できてよかったです。
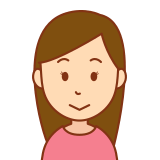
孤立しがちな凸凹子育てですが、今回も皆さんの貴重な体験やご意見をお伺いする事ができてよかったです。

今回は、“変わり者”と捉えられがちなギフテッドのお子さんですが、ご参加いただいた方の中から、お子さんが学校の中で明確ないじめを受けるという経験を共有していただいた方のお話しには、本当に私にも学びになりました。
たまたまでしょうが、私の息子も、そして娘も今のところ、どこかであからさまないじめの経験を持ったことはないだろうと(親の私は)思っています。ただ、息子の場合は友人関係が上手くできずにクラス内で孤立しがちだったことはありますが。
しかし今回はそうではない、明確ないじめの実態に関するお話は、参加者すべてに衝撃とともに胸にグッサリ刺さったものと思います。いじめなんて、本当に卑劣、許しがたいことでしかない。未熟な子どもだからと言って、流せるものではありません。
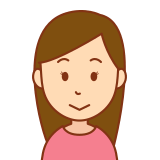
もし息子だったら、と思うと辛くなりました。
私もそう。話してくださり本当にありがとうございます。視野がまた広がったので、これからまた深く考えていきたいテーマです。
そしてやはり今回も参加者のお子様の多くに共通していたのは、“不登校”という実態でした。早ければ小学生の早々に、遅くとも小学校の高学年で、多くの高IQのお子さんがみな学校から離れるという決断をしていたことは顕著でした。(←今回は、1人を除き全員ではなかったことを申し添えます)
何が一体そうさせたのかは多様なことです。
ちょうど今のこの時期は、地域によっては夏休みが明け、学校が始まっている校区もあるので、当サイトへも始業式に行けたとか行かなかったとかの色々な声が聞こえてきているところです。みんなよくやってるよーーー!と叫びたい。
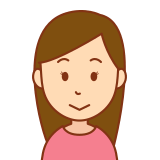
ひとまず今日は1時間目から登校できましたが、どぉやった?って軽く聞いたら、
「楽しくもないしイヤすぎるわけでもないけど明日は行かん」との返事でした。

私は最近思います。
不登校って、なんなんだろう、と。
息子に関して考察すれば、彼は独学ができる子でもあり、基礎学習や学力の面のみでは学校などに行かずともさして困ることはなさそうです。多分息子の勉強それ自体であれば、息子がやろうと思った時からいつだって取り返して行けるだろうと確信できる聡明さを私の息子は持っています。(そのスイッチがどこにあるのかはまだ不明ですがね、笑。)
しかしながら、最近に出版され当サイトでも紹介させていただいたこちらの書籍(↓)にもあるように、『成長に社会性抜きでは考えられない、ここが最大の難点』というのは私もそうであろうと頷くほかはありません。
IQの高さは、社会で生き抜く力ではないのです。
社会の中で求められるのは、自らの力を社会のために、世のため人のために活用していくスキルであり、『メタ認知を身につけるには、集団の中で社会性を身につけることがいちばんの近道』であると書かれることには深く考えさせられます。
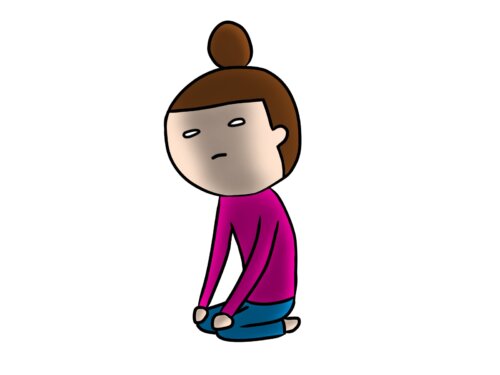
集団の中で社会性を身につける。
嫌なことも嬉しいこともある中で、自己理解と他者理解を育んでいって、それらが能力を引き上げる。
分かっているの。
だけど、今の息子を見れば、学校に行かなくなって、その次の居場所を求める一歩がすごく重くて辛い。
不登校って、なんなんだろうと思います。
一つ、今の息子を見る今の私が思うことは、不登校それ自体はとても多様だし一現象にしか過ぎないものかもしれないけれど、不登校がまだ学齢期の子供に与える影響は深刻だということです。
『自分は頑張ったけど受け入れられなかった』
『普通の中に馴染めなかった』
『ダメだった』
そんな極めて強烈なドロップアウトの体験を、幼い子供本人に刷り込んでしまうことが、不登校が子供に与える最も深刻な悪影響ではないでしょうか。
もちろん人生はまだ長い。
何があっても、人生はずっと続いていきます。一度のドロップアウトの経験なんてなんでもないと思える日は必ず来ると大人の私は思えるけれど、それを今その渦中の子供にもそう思えというのはまた難しいことだと思います。
社会の中で、不登校が子供にとって負の経験にならないような、そんなシステムをどうか求めていきたいと、私は切に思います。
ーーー書籍紹介ーーー
不登校の捉え方、社会の中での不登校、学術的背景を年代を追って考察している書籍です。私はかつてあったという“学校の聖性”が説かれる記述がとても面白くて印象的です。そうだよね、昔は尊敬される人が教師だった、学校は立身のために意欲を持って行く場所だった。義務教育の背景もまたとても勉強になりました。

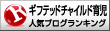

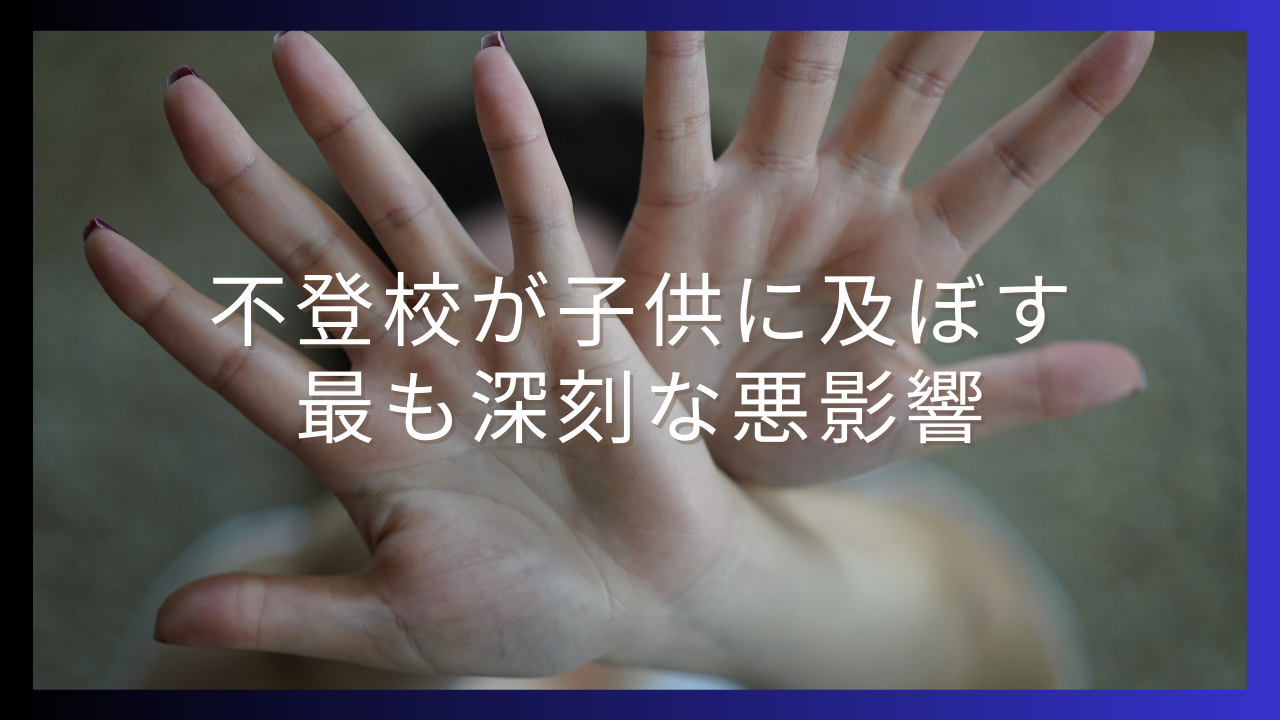




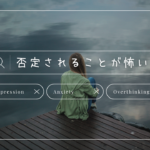
コメント