みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
先日私は当サイトの記事において、私が不登校という現象が子供に与える悪影響で、最も深刻であると感じていることを書きました。
今の私は、息子を見ていて感じるのですが、不登校それ自体の是非はさておいて、不登校が子供に及ぼす深刻な影響は、まだ幼い子供にすぎない当事者に強烈なドロップアウトの経験を植え付けてしまうことだと思っています。
学校に行けなくなったこと自体が、子供にとって強い負の経験になってしまうのです。
「自分はあのときダメだった」と、自分の存在意義を否定されてしまったようにまで感じている子もいるかもしない。
そしてその後の自信がなかなか育っていきません。
現象としては、単に「そのときその学校に馴染めなかった」というだけのことなのですが、強い自己否定感を抱えてしまう子供がいることが私はとても深刻なことだと思います。
居場所は他にもたくさんあるよって思うよね。だけど不登校になる子って、基本的にとても思考が深い子達だと思うのです。ついつい色々と考えてしまう子どもらなので、次の一歩も怖くなってしまっているのかもしれません。
例えばですが、学校だけではなく、その他の選択肢がもっともっと存在感を増していけば、不登校もそれほと強い負の経験にもならなくなる日はくるかもしれないなと思います。フリースクールは学校に行けなくなった“代わりの場所”ではあるのですが、代替という位置付けよりももっと存在感が上がっていって正規の居場所として機能して、自発的にそちらを選ぶことがより一般的になる日が来たらこういう子らには違うかも。完全に学校制度が解体されるような話ですが。また、昨今ではメタバース空間なども不登校支援の居場所の一つに言われますが、それで満足できる子って本当にいるの?と昭和生まれの私は感じてしまっています。何もないよりマシだろうとは思うけどね。子供の満足感が他の場所では得られにくいことが課題です。
さて。そんな我が家の、次の一歩がなかなか出ない息子の話。

あー、やっぱり否定されることが怖いんだな。
と、私がそう感じてしまったちょっとしたエピソードが最近にもありました。
我が家では、子供らも“朝ドラ”が割と好きでして(←私が見るから)、今期の朝ドラ『あんぱん』もみんなで喜んで観覧させてもらっています。
少し前に、この朝ドラの中で“ノブちゃん”がお勤めしていた会社から解雇をされたということで、クビになったことにガックリ肩を落とす、そんなシーンがありました。
私はこの場面を、深い共感を持って見ておりました。私は、あの時代に女性が外で働くことそれ自体に大きな壁が存在し、どれだけ能力があったとしても軽作業が主な仕事で、何かを新しく生み出したり価値を作ったりするような責任ある仕事に取り組むことは不可能でさえあったことを知っています。事実、私が若かった頃に大学で研究者兼教員を務めていた平成後期さえそういう側面は残っていました。当時は若くて小柄な私などは、変わり者のオジサン研究者達の男性社会においては時に嫌な思いもしたものでした。
だから私はこの場面を、『まぁそんなこともあるわな、今までよく頑張ったくらいだよ、落ち込まないで、あなたが悪いわけじゃない』と思いながらしみじみ見ていたその時に、後ろで息子がポツリと何か言いました。

おれなら、無理だ。クビになるとか、俺にはぜったいに耐えらない…。
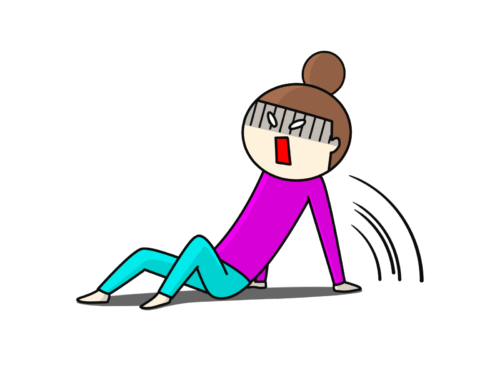
私はとても驚きました。口について出るほどに、息子がどれだけショックを受けたことか。
何より息子は割と、自分が当事者でなければ「他人事」は「関係ない」とバッサリ切り捨てることもあったり(小学校での道徳の授業とか、本当に参加しようとしていなかった😅)して、他人事にはあまり関心を示さない子なのだろうと思っていました。だけどそんな息子が今は、ドラマの中での一場面に、ついついポロッと声が出るほどショックを受けるとは思わなかった。
私は息子に言いました。

そっかー。なんでそう思うの?

だってクビになるなんて、どうしたらいいかわからないよ。


そっかそっか、そうだよね。びっくりするよね。
んー、それでも実はね、お母さんはそうは思わないんだよね。むしろこの“ノブちゃん”は、クビになって良かったかもしれないなとお母さんは思っているよ。

?

だってそれは、合わない場所に明日からも居続けなくて良いってことだよ。そりゃあその時はショックを感じるとは思うけど、クビや解雇は社会のなかではよくあること。お母さんだってこれまでも合わない場所から離脱したことは何度もあるよ。

合わない環境から離れることや離すことはお互いにとって良いことなんだよ。それはどちらが悪いわけじゃなくて、“今そのときは”合わないってだけなんだよ、その人まで否定されているわけじゃない。
そんな単なるタイミングだけの問題なんだと、お母さんは思うけどね。

ふーん。言われてみればそうかもしれない。そう言う考えもあるのかー。
そう言って、息子はトントンと階段をのぼって自室へと引き返して行きました。
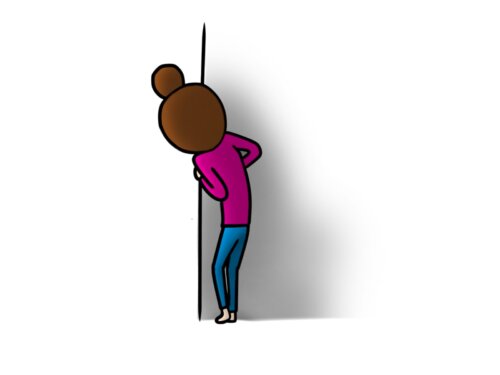
このエピソードから、私が感じたことは2つです。
一つは、息子には、多様な考え方がまだまだ入る余地があること。何かのきっかけさえあれば、対話によってそれは十分に理解がなされることがわかりました。
もう一つは、集団生活の経験が人より少ない息子の世界がやはりとても狭いこと。だから心も広がっていきません。学生の間は、大人が決めた限られた教室の限られたメンツの中での環境や順位に押し込められて、その中でのはみ出し禁止が徹底されて図られました。社会人になればそれらは全て自分で選べることを、私はもっと、もっと息子に伝えなければなりません。
そう、思考が深い子どもたちは、先が見えないことにさえ、怯え、考えすぎています。
だけど私は息子のように、思春期という時期をとても不器用に生きる子供も、それはそれで彼らしいなと思います。何も考えずに学校生活を過ごす子もいる中で(←私の教員生活からの私感です、マジで。)、思考が深い彼ら彼女らにも、知らず知らずにも生きる力が身に付くこともあるだろうと思うのです。
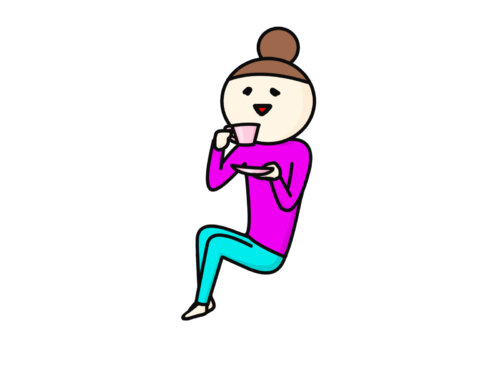

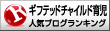

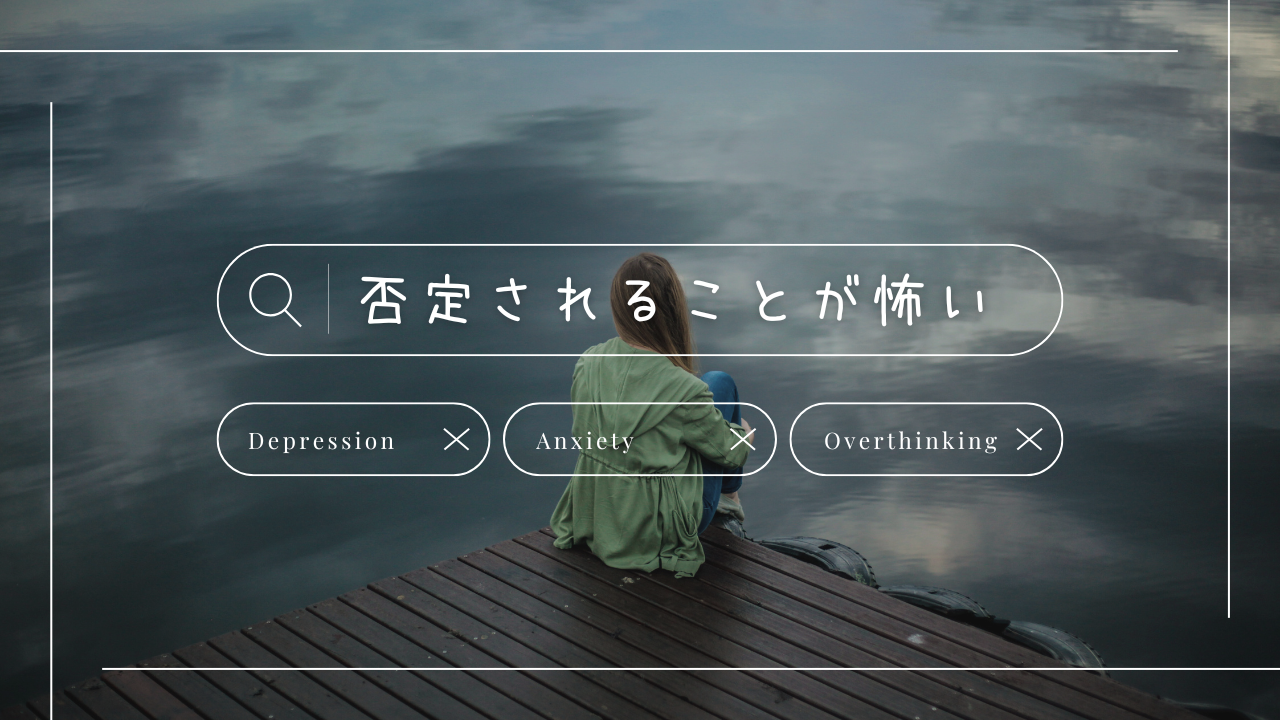
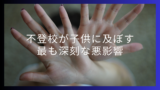

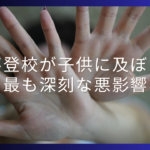

コメント