みなさんこんにちは✨
今日も当サイトを見にきてくださり、ありがとうございます。
最近私が読む本は、すっかり発達障害に関する書籍が大半となりました。少しでも息子を理解し支える助けにならないかと思い、色々な情報を集めています。
それが最近、同じ本を2回注文したりすることなども出てきました💦本が届いてから読むうちに、「あ、これ読んだわ、うちの本棚にあるやんけ」って気づくのは悲しい😭
そこで、読んだ本は何らかの形で記録しないといけないなと思いました。
せっかくなので少しの感想を添えて書いていきます。
今日はこの本(↓)。
子どもの発達障害誤診の危機/著 榊原洋一
普段の生活の中で『発達障害』という言葉を本当によく見聞きするようになりました。
医療や教育現場の専門家のみならず、社会に広く発達障害への認知・理解が広がりつつあることを実感しています。
一方で、情報が増えれば増えるほど『正しい情報』と『誤った情報』は混在し、それはいつも無知な人達を惑わせます。
間違った情報に振り回されないためにも、勉強することは常に大切です。
特に発達障害は、健常な人とも地続きのグラデーションの障害です。
『誤診って、絶対にあるだろうな…。具体的にはどんな事例をいうのだろうか。』
そう思って、私は本書を手に取りました。
なぜ誤診が生まれるか
本書において著者は発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム障害、学習障害)の誤診が生まれ得る理由をいくつか挙げ、丁寧に説明を重ねて書かれています。
一つはやっぱり発達障害が急激に社会に認知されるようになったから。そのため専門家の間でも今なお見解に多少の違いがあることを挙げています。
また、その診断は医師の診察によりなされるものであり、画像検査や遺伝子検査のような確定診断の基準となるテストがないことも影響していると書かれています。
その結果、学校や職場の中で、人間関係が上手く築けずにいる人がいると、「あの人(子)は、アスペルガー症候群ではないか」とかそのような特性のある人のことを「アスペ的」と行ったりする風潮が生まれたのです。
小児科医の私のもとに、自らアスペルガー症候群ではないかと疑ったり、職場の上司から人付き合いが下手だと言われたと言う理由で、受診する大人が増えました。もちろん、そうした人の大部分はアスペルガー症候群ではなく、単に人付き合いが苦手という人たちでした。
第3章 過剰検査と過剰診断より抜粋
いるいる。人付き合いが苦手な人って😅
それも発達障害とされては、本人にとっても医師にとってもなんとも気の毒な話だわ。
また、本書では本当にサラッと書かれているだけですが、私は
『一般的にはギフテッド(gifted)と言われる特に知能指数(IQ)が非常に高い子供が、往々にして自閉症スペクトラム障害やADHDといった発達障害と誤診されることが多い』
という記述が気になりました。
IQが高いことが、どうして発達障害のように見えるのだろう?
すごく不思議です。
私はこれまで私の誠に勝手なイメージで、発達障害のある子の一部にはIQが非常に高い子供がいるのだと思っていました。(私の息子もIQは高めです)
しかしながらこの記述は全く逆で、IQが高いことで発達障害の特性ように見える個性がでうるような書き方をされています。
『特に米国ではギフテッド児(者)に対する社会的認知が進んでいるにも関わらず、そのアメリカにおいてさえ発達障害と誤認・誤診されることが多い』と続いており、誤診が増えていることへの問題提起がされていますが、残念ながらその詳細には触れられていません。
もう少し詳しく知りたかったな。とはいえ私はこれでも元研究者。近いうちにそのことが分かる文献など探してみようと思っています。
誤診の原因についての話に戻ります。
発達障害を抱える人には高い頻度で二次障害が認められ、そのことが発達障害の診断をより困難にしているとも書かれています。
そのため発達障害の診断はどうしても医師の個人的な経験と判断で決定する”匙加減”となることが起こり得て、それが誤診や過剰/過少診断の原因になっているということです。
本書では他院で「集団の中で指示が入りにくい」「こだわりが強い」という理由で発達障害と診断されたお子さんも、別の病院では診断の対象外となる事例が多数挙げられており、私はこれを非常に興味深く読みました。
特に乳幼児期の子供は、慣れない環境で知らない人と向かい合った時には人見知りで普段通りにはできないことがある。それに関しては誰も異論はないでしょう。
だから一人一人にしっかりと時間をかけて診察し、慣れてくるのを待ってから細やかな観察を開始することでもだいぶ違うのだと書かれています。
乳幼児健診の慌ただしい場面が思い起こされます。
私の息子も1歳半健診で言葉の遅れを指摘され、療育機関に相談に相談に行くよう勧められたことがありました。
その際、私も確かに『この医師は、いったい何分間この子を見てそのように言うのだ!』と戸惑い憤慨したことを思い出します。(うちの場合はここで療育を受けず、10歳にもなるまで彼の発達障害に気づかなかったことは大いに悔やみ反省しています…)
限られた時間で大勢の子どもを診る体制と診断基準の限界に関する記述は現場が目に浮かぶようであり、私も大きく頷きながら読みました。
発達障害は治る: 診断名を取り消すことができる日が来る
本書の第6章は「発達障害は治る」というタイトルです。びっくりしました。
私は発達障害はその人が一生付き合っていく生まれ持った個性なのだと理解しており、「乗り越える(outgrowth)」ことはできても「治る (heal)」こととは違うと思うのです。
そのような思いで読み進めましたが、つまり発達障害、特にADHDでよくみられる一部の特性においては、診断の根拠になった症状が子供の成長・人格ができてくるとともに軽快することが多々あるのだという話でした。
症状が軽快し、それがさほど困難をきたさないようになった時点においては診断名が不要になる日が来る。
私はいままで一度ついた診断名は一生付いてまわるものなのかと思っていましたが、一度ついた診断名も不要になった時点で将来取り消すことが可能なのだ知ったのは発見でした。
発達障害の特性をしっかり理解して、困難を乗り越える手筈を整えていく。そうして成長していくことでさまざまなスキルを獲得し、治るとまではいかなくても不自由がない生活を送ることもできるんだ。
私は息子の発達障害について、なんというか、もっと硬直したイメージを持っていたように思います。
本書を読み、発達障害はもっと柔軟に考えて良いのだなぁと思いました。肩の力が抜けた思いです。

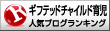

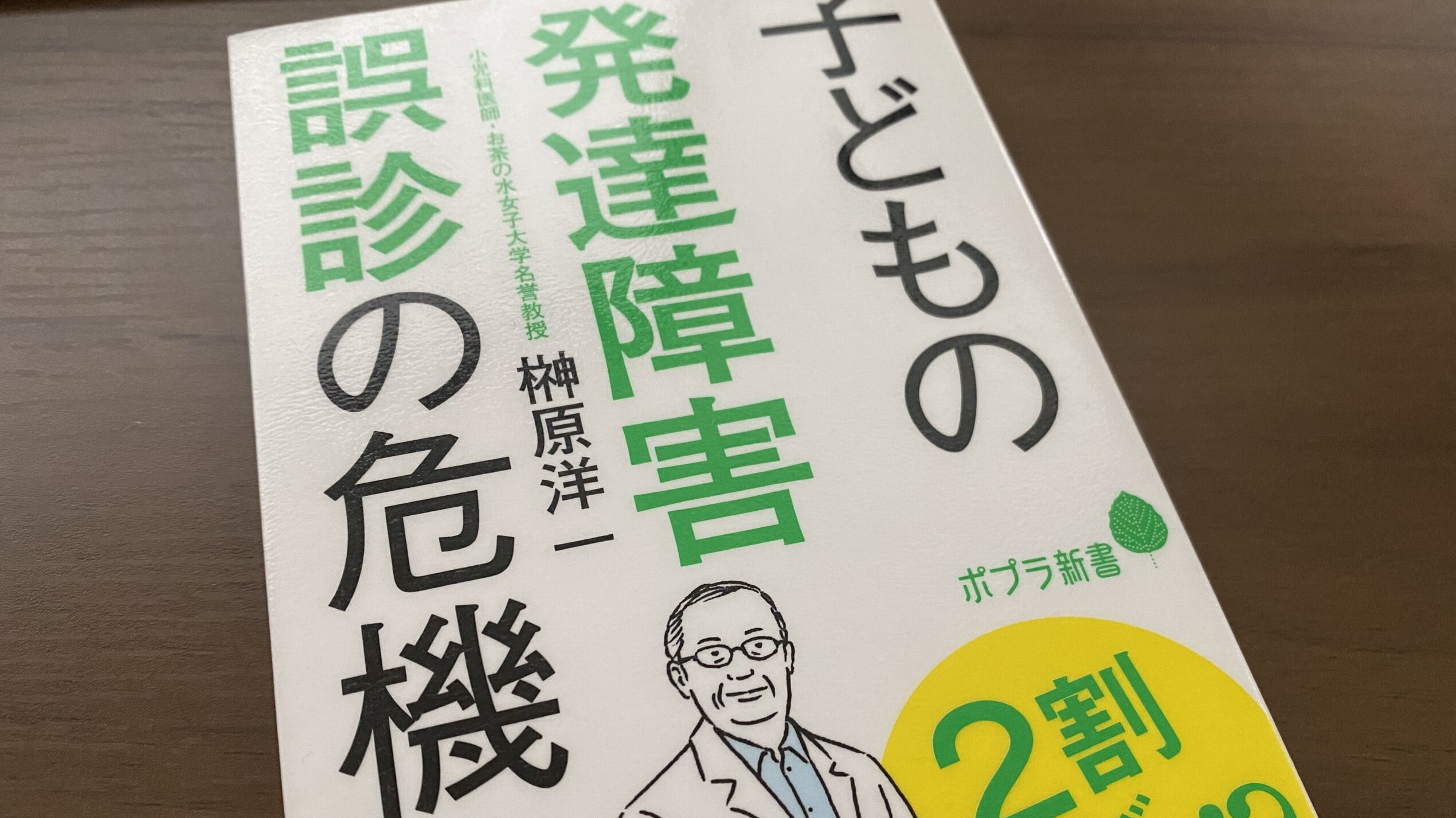




コメント