みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
先週に、発達障害に関連して新しい論文が発表されました(↓)。私もザッと拝読し、時事に即したテーマであるし、着眼点にびっくりしたし、とても革新的だと思ったので、ここに情報をシェアします。
研究者が命がけで書く“論文”とは、研究成果を世に知らしめて人類の財産とするために、種々の専門誌に掲載される形で発表されます。その専門誌にも、“権威”とでもいいますか、研究者のあいだでも「一生に一度はこの雑誌に研究成果を載せてみたいぜ!」という目標とでも言いますか、なんというか、ある種の“格”や“インパクト”を指し示す序列(のようなもの)が存在します。
なかでも『Cell(セル)』は別格です。“よほど”の発見でなければ手は届かない、超一流の科学誌といって良いでしょう。革新的な研究成果を自身の手で生み出して、厳しい審査の応酬を経てそこに論文が掲載されることは、紛れもなく全研究者の憧れです。そのCellに、発達障害への最新の知見が報告されていたのだから、読まないわけにはいかんだろう。

テーマは“発達障害とAI”でした。大規模言語モデルを用い、自閉スペクトラム症(ASD)の診断における臨床医の経験と直感(clinical intuition)の思考過程を、AIにより説明しようとするものです。新しい発見がありました。すごいよなぁ。
簡単に内容を要約します:
- 自閉スペクトラム症(ASD)は人口の1〜2%に見られるとされ、客観的な診断の指標を求めてこれまで多くの研究が行われてきた。
- しかし、そうした手法でASDを正確に診断することは、未だ医療現場では実現していない、特徴があまりに多因子的だから。
- その診断は、今なお各医師の経験や直感に頼っていることが実際である。
- 自閉症の診断に係る医師の診療記録(4,000件以上のカルテなど)を、AIにを学習させた。
- その結果、診断の決め手となり得る重みについて、“解釈可能なAIモデル”を構築できた。
- DSM-5(診断基準)と照らし合わせ、診断に最も重みがあったのは、「常同行動」「特別な興味」「感覚過敏」。
- それらは従来重視されてきた「社会的なコミュニケーション上の困難」よりも重みがあると明らかになった。

いや、私はこの論文をパッと読んだだけだし、誰とも議論をしていないままに衝動的にこれを書いているところなので、理解は甘いことをあらかじめ含めおかせていただいても。
それでもこの一つの結論の書かれ方はとても印象的でした。
息子もクルクル回る子供だったし、今もつま先でパタパタ音を立てて歩いているし、
似た資質を持つお子様方の中には、飛ぶ子(いわゆる「ぴょんぴょん系」)も、感覚過敏の強い子供もいることを、私も重々知っています。
自閉的であるという特性は、成長過程で支援を要する対象ですが、その早期の気づき方の一つにおいて常同行動や感覚過敏の有無が、今まで考えられていた以上にずっと重要な指針になることを、この論文は示唆していると読み取れました。
“大きくなるまで、子供の困難や特性に気づけなかった”
そんな親の後悔が、いつか減っていくかもしれません。
膨大な情報量の取り扱いは、まさにAIの得意な分野です。これだというマーカーが見つからなかった疾病にも、AIと言語モデルを用いることで、どこに住んでいてもいつの時代に生きていても、いくつも医師を訪ね歩かずとも、
これまでの全医師の経験や直感・センスに基づきつつも客観性のある診断を受けられる時代がやって来るかもしれません。想像すると、近未来感がありますね。ワクワクします。
この研究は、これまでの技術と理論が積み上がってきたからこそ、今の時代だからこそ実現可能となった成果であり、これから先の新しい視点を切り開くという点でも重要なインパクトを感じます。
さすが、Cellだ。
時代は確かに進んでいることを感じます。
研究者の地道な努力に、心からの敬意を。
ご関心のある方は、お目通しいただいてはいかがでしょうか。(私も誰かと議論したいです🙌)
ーーー
下記のイベントが、もう来週となりました。まだご参加を受け付けておりますので、ご関心のある方はぜひお申し込みください。
📢2025年春の情報交換会(対面形式)
開催日時:2025年4月28日(月)10時〜15時頃を予定
開催場所:東京都内港区ベイエリアの会議室
参加費用:お1人あたり5,000円を申し受けます(関心のある学生さんは、1,000円/人)


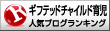




コメント