みなさんこんにちは✨
今日も当サイトを見に来てくださりありがとうございます✨
この週末は息子の小学校の”2年ぶり”の運動会だったので、週明けの月曜は振替休日でした。
せっかくの平日休みなので、私は息子と2人で出かけて用事を済ませ、お昼には息子が大好きなお寿司を食べて、帰りには本屋さんと図書館にも寄りました。
それで私と息子はここ2日ほど読書三昧。とてもゆったりと過ごせています。
今日は、私が読んだ本の記録です。
我が家の息子の融通の効かさなさ、衣替えの難航と混乱。
そんな息子を見守るにつれ、私の心は湧いたりしぼんだりはするけれど、どうしても消えることがない『この子は社会に出て働くことができるのだろうか…』という悲観と不安が揺らめきます。
自然と、この本を手に取る運びとなりました(↓)。
発達障害の子が働くおとなになるヒント/ 著 堀内祐子、柴田美恵子
この本を手に取ったきっかけ
私の息子は、診断は未だ受けていませんが、明らかな発達障害の傾向がありそうです。
急な予定変更には全く対応できなかったり、
片付けや物の管理が致命的に苦手であったり、
許容できない事態に対してはパニックを起こしてしまうこと、
今夏の衣替えでは他人(親)の意見を全く聞き入れることができなくて、しょうもない嘘までついて、その場凌ぎの誤った対応まで編み出しました。
息子は、学力が低い訳ではありません。本人も、勉強に対する苦手意識は持ってなさそう。
だから私は息子に学力を伸ばすことで自信のきっかけを育んで欲しいと願いながら、今は中学受験を目標にして、少しずつ勉強をさせています。だけど、計画的に“勉強を進める”という作業自体にも、おそらく“普通”のお子さん以上に手がかかっていると思います。
何しろ、消しゴムが見当たらないだけで、息子は静かなパニックを起こしてフリーズしてしまうのですから…(関連記事をご参照ください↓)
私は、このような息子と向き合い始めてから心配でした。
この子はたとえ人並みに勉強ができたとしても、社会で働くことは困難なのではなかろうか。
社会に出てうまく行かないことが続いたら、きっと本人も辛いだろうと思えてきます。二次障害のきっかけにさえ、なってしまうかもしれません。
それを避けたい。
この子が社会人として活躍する日のために、今の私はどんなサポートができるのか。
きっと素敵な青年に育つと、私は息子を信じています。
だけど信じるだけじゃなくて、何か、具体例かヒントが欲しい。特に最近、私はそんな気持ちで過ごしていました。
そんな時。
ふらりと立ち寄った本屋さんで目の前に、こんな絶妙なタイトルの本を見つけてしまった。
手に取らないわけに、いかないじゃないか!
ってことですぐ読みました。
“自立”させる人、する人
本書の冒頭。著者の堀内さんには4人のお子さんがおられますが、それぞれ全員が発達障害の診断を受けているとのことでした。
そりゃぁ…大変だ…。一体どんな毎日の暮らしだったんだ…。
ゾッとしつつ本書を読み進め、私はすぐに4人のお子さんを心身ともに健康に育て上げられ自立させてきたことに心からの尊敬の気持ちを持ちました。
印象的だったのは、とっても素敵なご家族だなぁということです。
兄弟がそれぞれ困っていると年長の兄弟がサポートしたり、それにご主人もとても協力的(しかも経済力もおありで頼りになる)で、家族が一致団結しているなぁと思いました。
いや、『父親が協力的』なんて、当たり前。書くまでもないわ。だって親だもん。
(本当ならそんなことわざわざ書くことでさえないんですが、ちょうど私が先日に後輩が離婚したという話を聞いたばかりでもあり、世の中には残念ながら“無責任”だったり“未熟”な男性もいらっしゃることが現実だなぁと思ったばかりなので余計に印象に残りました。まぁそんな話はさておいて。)
本書はそんな一致団結したご家庭での、お子さんを自立させることを目指したご家庭の方針の紹介と、それを受けて自立しようとしていく子供たちの話です。
特に、思春期から大人になるまでの時期に焦点を当てて書かれており、本書はその点でも私にとってとても参考になるものでした。
それぞれのお子さんの発達障害の特性は個々に特有であり、お子さんごとの困りごとへのご苦労や、不登校などの二次障害、不登校期間中の著者の葛藤についてもとてもよく書かれています。当時は、きっととても苦しかったと思います。
それらを乗り越えていく時期の、ご両親とご兄弟がいつも味方でいることの心強さはどれほどか。
そして然るべき時期にはそれぞれが“自分の良いところ”を見つけて自立に向かっていくご様子は、とても立派で励まされるものがありました。
子供には育つ力、自立する力がきちんと備わっているんだな。
私はそれを信じて、息子の良いところを支えて伸ばしていくことを少し意識すればいい。そうして毎日楽しく暮らしていければ十分なのだと思えました。
読んで良かったと思います。
タイムリーに、求めていた本を読めました。
発達障害や不登校のお子さんの将来を悲観したり不安を感じている方は、今すぐまずは一読することをお勧めします。悲観や不安の時間って、もったいないよね、何にも生み出さないもの、と思えてきます。
発達障害の“診断”を受けることの意義を考えた
さて、私はこの記事の最初に
“私の息子は、診断は未だ受けていませんが、明らかな発達障害の傾向がありそうです。”
と書きました。
そう、当サイトは【10歳から向き合う発達障害】としているのに、また、息子については昨年の夏から親も、本人も、学校や塾などの周囲の方もみな『発達障害の傾向のある子』として対応しているにもかかわらず、当の息子は実は未だに医療機関を受診しておらず、障害についての明確な診断を得たことはないのです。
敢えて、診断を受けることを避けてきたわけではありません。
ただ、機会がなかったという感じです。
私は、息子の“障害名”がどうこうよりも、息子自身にしっかり向き合い、彼の特性を一つ一つ理解していく方がはるかに大事であると考えていました。
それに、周囲には理解のある友人や、教育相談では親身に意見しサポートしてくださる専門家にも恵まれているので、今更息子の障害名なんかは、私にとっては言ってしまえば“どうでもいい”ことでさえありました。
そんなわけで私は息子を受診させることのメリットを感じていなかったというのが実際です。
だけど、この考えには最近迷いが生じていました。
先にも書いた、今夏の衣替え事件がきっかけです。
やっぱり彼には出来ることと出来ないことが、どうしてもあるんだな、と私は改めて思い知りました。
また、息子がこれから自立に向かうにあたり、息子は周囲の理解と助けに恵まれる必要が絶対にあると改めて思いました。
そしてその際、やっぱり明確な“診断”を持っていた方が、親も本人も周囲に説明しやすく理解を求めやすいのではないだろうか。
私はそのように考え始めています。
少しずつ息子を医療機関に受診させることを考えていたところでした。
だけど実際どうだろう。
診断名がなくても、これまで息子はなんとかやっている。周囲のサポートも必要なところは求めていけている。
息子はナイーブな子供です。診断がつくことが息子の自尊心を傷つけるのではないだろうかとも心配でした。
今月はじめの教育相談で、担当の臨床心理士さんにも相談しました。
『この子はやっぱり発達障害があるのは明らかであると思いますので、今後のために診断を取っておいた方が良いのではと感じています。診断を受けることの意義について、教えてください。』
すると臨床心理士さんはこういう意見でした。

診断を受ける意義は、医療的治療や福祉につなげることが大きいです。
息子さんの場合は、継続的な服薬治療が必要な状況ではないと思うし、生活面ではご両親が万全の体制で支援をすることが可能な環境に恵まれています。そういう意味では、診断を受けることは今は必須ではないと考えます。だけど、理解を求めやすいという点では賛同します。
一方で私は、言葉通りにしか受け取れない息子さんに障害名がつくと、息子さんの意欲や態度に影響が出ることを心配してしまいます。
どうするかはご両親が決められることです。ご両親でよく話し合ってみてください。
うへ〜。そう言われちゃまた悩んじゃうな😅💦
そんな状態の私が読んだ、この書籍。
”診断”を受けることの意味やメリットについて丁寧に書かれていて、これも私が今求めている情報の一つに巡り合ったような気がしました。
4人のお子さんたちの診断を経験されて、診断を受けることを今後の支援にどう活かしていくのか、出来ないことばかりを論うのではなく、診断が親に本人にもたらす本当のものは何だったのかが本書では項を割いて書かれていました。
とてもわかりやすく、大きく共感する部分がありました。
”診断”は親を支えるものであってほしい。
そんなメッセージが伝わってきた気がしました。
これを読み、私はいま息子本人と一緒に”診断の意義”について考えることを始めています。
本書を読んで、”息子と一緒に考えること”がベストだと感じました。息子の意見も聞くことができて、私たちは日々考えを深めていっています。(いずれまた当サイトにも書こうと思います)
本書を読んだことで、私も息子も(+夫も)一歩前進した気持ちになれました。
求めている時に必要な情報に巡り会えることもまた運命だな。ありがたいことだ。
私たちはきっとうまくやっていけるだろう。
改めてそんな前向きな気持ちになった、良書との出会いでした。

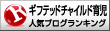

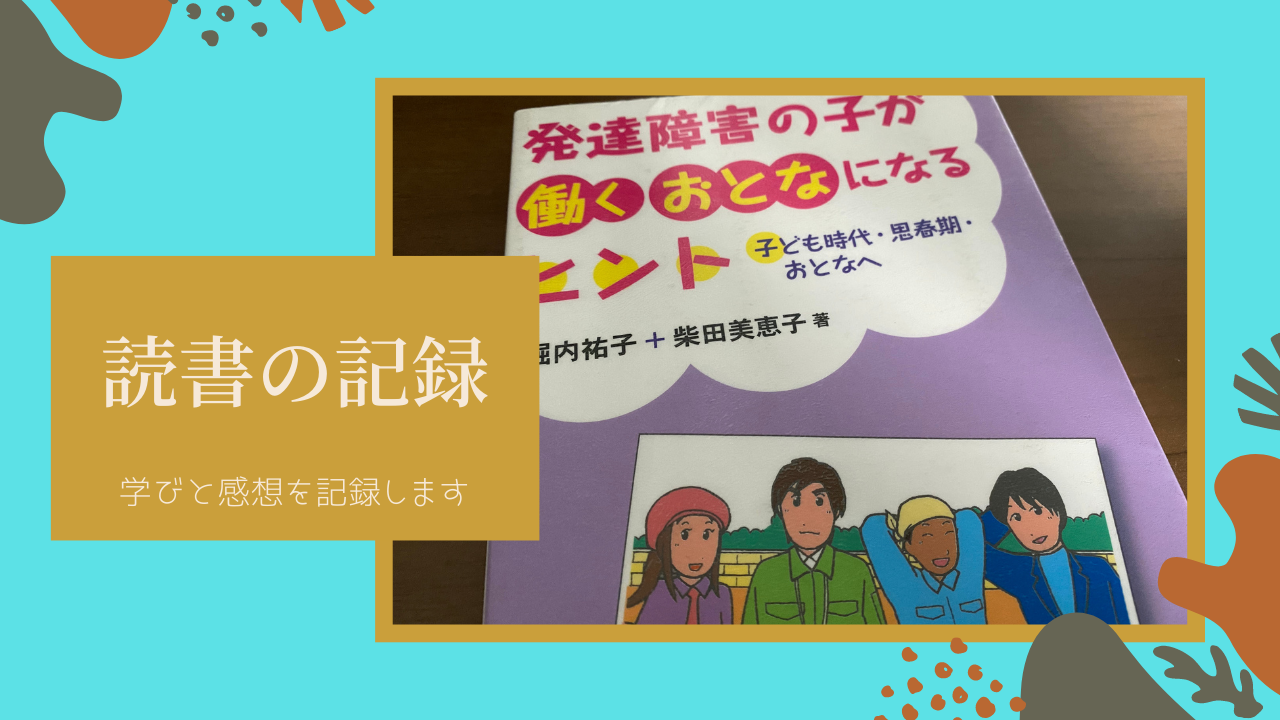






コメント