みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
ちょうど先週末の新聞で、おっと目をひく(私にとっては)良いニュースが飛び込みました。こちらは友人より送ってもらった新聞記事そのものであり(↓)、また、オンラインの新聞媒体でも広く報道されました。
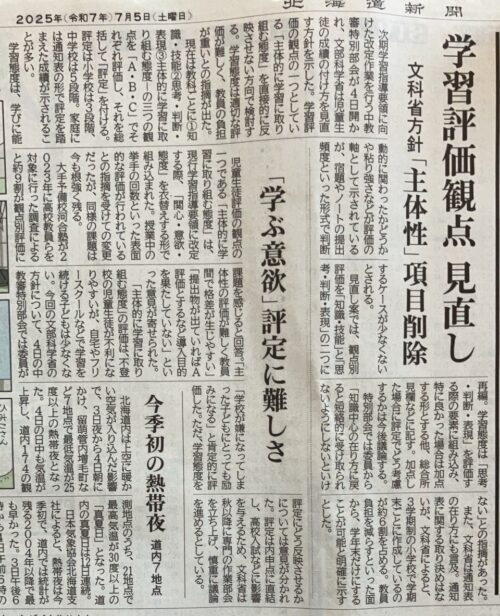



ちょうど当サイトでもそのようなことを最近書いたところでしたし(↓)、賛否(否というほどでもないが)を含む多くのご意見を聞かせていただいていたところでした。
なんとタイムリーな動きだろうか、ずっと待っていたものが認められ動き出し始めたことを感じられて、私はついついニヤリと笑う。

私自身も、この“内申点”というものにより進路を狭められたことがある当事者です(私に取っては結局は“結果オーライ”な進路ではあったけれどもね)。子供だった当時の私でさえ、この評価軸の人質性には疑問と憤慨、強い反発を感じていたものでした。
文科省の今回の見直し案では、評価観点を「知識・技能」と「思考・判断・表現」の2つに再編し、「主体性」については評定に直接反映せず、特に顕著な場合に限って「〇」を記述するという柔軟な扱いに変わります。
小中高の成績から「主体性」評価が外れる:先生は生徒の内面を評価できるのか?より
実際に、私はいま、「今」の学校現場を知りたくて、ある通信制の高校と、別の全日制の高校で非常勤教諭を務めています。通信制高校に通う生徒の学力は多様であり、個性もさらに多様ですが、中には私と波長が近しい子もおりまして、そんな子たちは私に時々“本音”のような話を語ってくれたりします。非常に気になる話も聞きました。

私は中学校では成績がよかったです。4とか5ばかりでした。その「コツ」は、授業の終わりにいっぱい先生に話しかけることとか、「追加の課題がほしいです!」っていうこととか。そうしたら、やってもやらなくても先生は喜ぶから。

でも途中でなんか学校に行きたくなくなって、行かなくなりました。

ほえー、おまえさん、なかなか策士やのう。やりたくてやってるなら良いけど、やりたくないなら疲れるだけやん。

お母さんが、そうしたら良いっていうからやってました。

中学校の中では一体何が起こっているのか、私には全くわかりません。理解不能。なんなのこれ。こうした単なる「忖度」がこれまで「主体性」という軸を成していたのかと思うと真に悲しいとしか言えません。それが出来ない私の評価は低くなるわな、そりゃそうだ、心にもないことを発言させられるくらいならば低くて結構、理不尽だとは思うけどね。
一方で、そんな忖度優秀者が進学校に進んでも、授業内容的にそれが本人のためになるのかどうかも疑問です。ひょっこり進学校に進んだら、周りがあまりに優秀過ぎて伸び悩んだというエピソードも聞くからです。ミスマッチは誰も幸せにしないのです。
そもそも「主体性」などという個人の内面態度にすぎないものを、ただの教師という他人が評価しようとすること自体が極めて不自然です。
主体性とは、プロセス・過程に過ぎません。個々に人は違いますし、思考も効果も好みも違う。だから大人は、あなたたちはどんなプロセスを取っても良いけれど、自分なりに学業をしっかり修めていけよと応援すれば良いだけで、最終的な「評価」をするなら、それはその「結果」に対してこそ与えられることが公正であると、私はそう感じます。
つまり教師の役割は、結果を得た子をしっかり褒め、結果が伴ってこないのならばプロセスを工夫したり変えてみたらどうだろう?と一緒に試行錯誤を提案することなのかもしれません。
冒頭の、新聞記事の写真を送ってくださった友人の言葉が胸に刺さるものでした。
彼女のお子さんもまた、著しい高IQの子供であり、今の所学校にはなんとかかんとか行っているが不安定で、とても目が離せない状況であると聞いています。
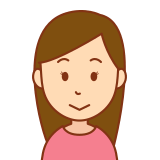
長男が今朝の新聞を読んで、「やった〜‼️」と言ったんです。
私、何も言ってないし、今までも言ってない気がするのだけど、本人は学校での評価が低いことに気づいていたのかな?
見直す方針、ってことはまだまだ先なんだろうけれど。
うん、そうだと思う。
物事のエッセンスを掴むのが早くて鋭い子供達が高IQ児という子です。
きっと気づいて感じていたんだと思うんだよね、その理不尽さに、そのあまりの不合理性に。子供でさえ、ね。
ーーー書籍紹介ーーー
読まれた方も多いでしょうね。母親とは、難儀なものです。私も難しい手のかかる子を持ったために、“子供は全てを奪う”という表現は刺さったし、共感できる部分もあります。しかし「これまで母親には、そんな不満を口にだすことさえ許されなかった、憚られた」と、それこそがこの書籍の主題です。
人はそれぞれ違うんだ、どんな人が居たとしてもそれを決して他者がどうこういうことではないわけで、社会の中の一員としてのそういう人もいるんだねと、ただそれだけの話になれば良いだけなのにと感じました。
子供がどんな学びのプロセスでも、大人がどうこういうことではないのと全く同じ話です。
【夏休みに入ります】
私は今年はこの7月中旬(来週)から長めに海外に出ています。LINEも見られない地域もありますので、その間は当サイトの全ての活動をペースダウンさせていただきます。
7月末には帰国しますが、8月は出張、学会、昨年亡くなった実母の法事、夏の登山で全国あちこちに移動していると予想されます。
- 記事の更新→できる範囲でとなります
- 個別相談→予約が取れるところは可能ですが、場合によっては調整をお願いするかもしれません
- 8月26日に対面形式の情報交換会を開催する予定です→アナウンスは順次で。
- 7月14日に公式LINE参加者限定のオンラインイベントを開催します→公式LINEにご登録ください。
皆様も、どうか良い夏休みをお過ごしください!


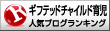

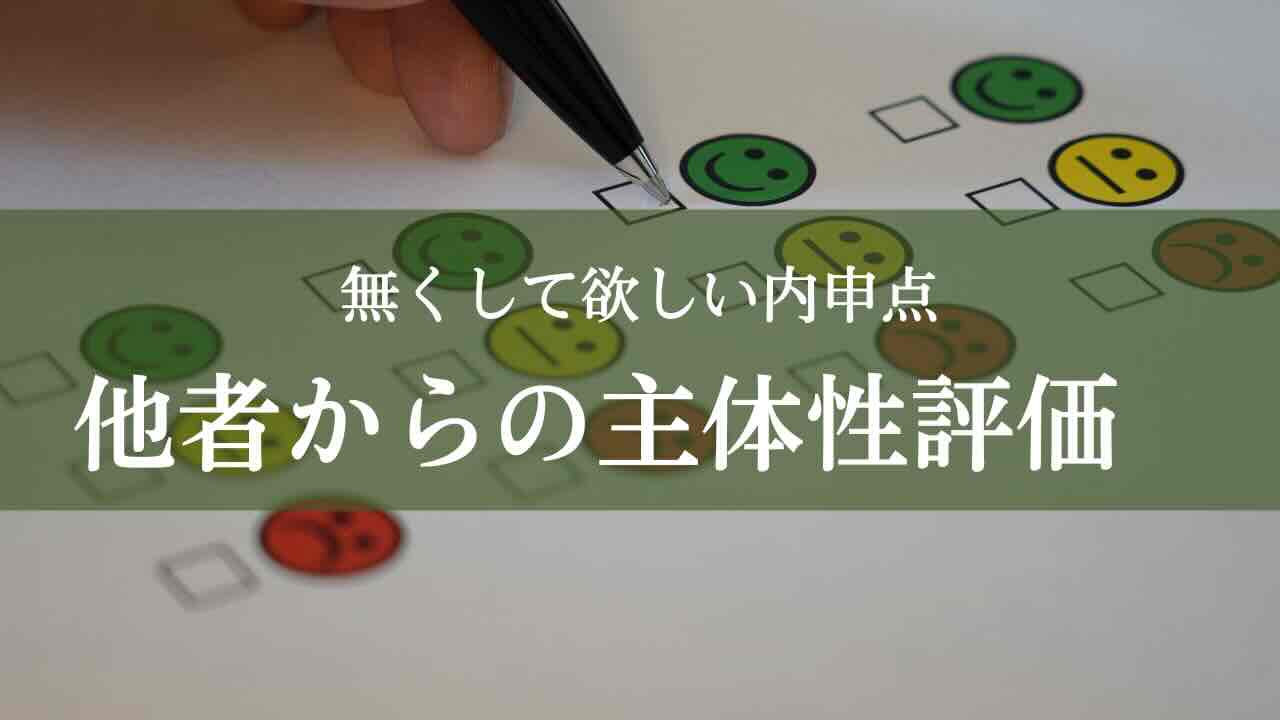


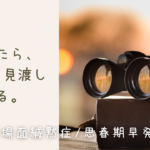

コメント