みなさんこんにちは。
今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。
今年7月のことですが、学習指導要領の改定を議論する有識者会議において、次期の指導要領の改訂において「主体性」という評価軸の比重が引き下げられることが広く報道されました。そのことは、当サイトでも“嬉しいニュース”として触れさせていただいたところです。
これまでも当サイトで主張させていただくように、私はこのような子供の意欲関心態度を、教師といえども他人にすぎないいち大人が測ろうとすること自体に強い疑問を持ってきました。私自身は“内申点”というやつで嫌な思いをした一人です。また、私はこの評価軸の人質性にも反発を感じているのです。
主体性?それは学業成績と連動するものでしょうが。
主体性がある子は自分なりに自分のやり方でやっていくし、相応に結果もついてくるはずなのよ。
その結果である学業の習熟度を、別の理由で減点するようなことが起こるから、不満やトラブル、子供の意欲喪失のもとにまでなるのです。
私は遥か昔ですが、自分が中学3年性の時に担任教諭に言われました。
『たとえ当日の試験が満点であっても、お前は進学校には合格できない』
『なんで私より点数が取れない人が進学校に受かるんですか?』
私は模試でも満点近い点数を取る子でしたが、理解できないことには断固従わない子供であり、通知表の評価、つまりは教師からの覚えはあまりよくなかったようでした。この時の私は、進学校は学力の高い人がほしいわけではないのか?と安直な疑問を感じました。そう、これは大人の望む通りに振る舞わないが勉強ができる子供に「それはダメなんだよ」と一方的な否定を押し付ける、私にとってはそんな軸でした。私が育ったのは地方都市だったので、今の東京のように私立の進学校もありませんでした。
こちらの記事(↓)は、多くの方のお目に触れたようで、たくさんのご意見やご感想をいただきました。そのことから、この評価軸に疑問を持ったり理不尽を経験してきた大人も青年も、実際にはかなりいるのだろうと感じました。
つい先日、この夏休み中に私は教育学の専門家でありギフテッド児を育てる母親でもある友人と会い、この話題にも触れました。
2030年を目処として、私の娘(小2)が小学生のうちにはきっと、この評価軸は速やかに評定に含まれなくなるという見通しをあれこれ聞かせてもらいました(←っていうか、決まったのなら今すぐ直ちに今学期からでも廃止しろよと思うけどね)。また、この改訂は、子供のためというよりも、子供の意欲や主体性という非常に見えづらいものにまで今の現場の先生方の手はとても回らないから、だから引き算の改訂となるのだとも囁かれていることを聞いてしまい、私はそれを複雑にも感じました。
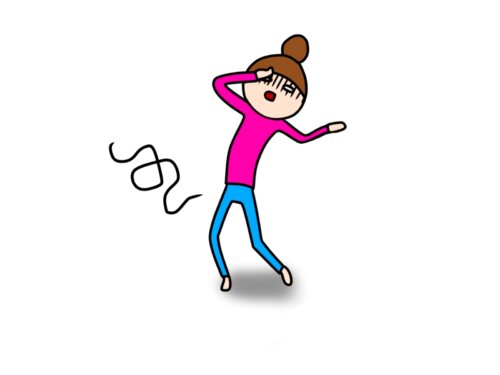
とはいえどんな事情であれども、先の記事でも書いたように、それで「やった!」と声をあげ、ホッと胸を撫で下ろす今の子供がいることも実際です。
現場の先生方も、大変お疲れ様でございます。少し負担が軽くなると良いですね。
高IQやギフテッドの子供達にとっても、この改訂は多少は前向きなものになっていくのだろうと期待しますが、長期的にはどうでしょうか。
この評価軸が握っていた人質性は、義務教育の先にある高等教育機関へのアクセスにこそ効いていました。少子化が加速する現代において、すでに高校は全入です。私立高校の授業料は無償化され、高校入試を撤廃して高校も義務教育化と構想する先駆的な自治体もあるようです。また、自分の時間を有効に使うためにと前向きに通信制高校へ進学する子供も増えていて、大学も経営方針が改められて学生に選ばれるよう統廃合がなされたりもしていています。
長期的な視点では、この先の時代はもはや内申点など不要となり“通知表それ自体”さえ不要視される、そんな日がくる予感もどこかしてきます。
その一方、最近では愛媛大学を中心として、教師を対象とした“特異な才能のある児童生徒”に関する研修パッケージの作成なども頼もしく進められているなどで、ギフテッド児へのニーズベースの支援であったり、すなわち今までになかったものの足し算となる改訂もまた同時に構想されています。
これ自体は、我々にとってはとても良いこと。
それぞれは個々に他人ですが、不思議なことにIQのとりわけ高い人たちには共通する行動特性があることはギフテッド児に接する人には自明のことです。そのことが、徐々に知らされてきています。
だから今の大人がその共通特性について知ろうとし、それを踏まえて子供達に接することができたなら、それはとても良いことです。
だけど心配なのは、やはり現場の先生方の“余力”ですね。私自身も今は教員の世界に入ってみておりますが、教員とは経験がものをいう仕事の一つですね。余力と、それを受け入れる土壌が今すぐあるのかどうかは気がかりですが、こういうものは動き出し、支流が合流して流れが太くなってこそ定着していくものであろうと思いますから、支流の合流に私は密かな応援の視線を注ぎたい✨
そんな足し算も良いのですが、私は今後の教育は、もっと引き算でも良いかもしれないとも思います。公教育は、複雑な形になりすぎました。
この子は発達障害、この子は高IQ、学習障害、身体の障害、海外留学、賞を取らせ、漢字や英語の検定を勧め、保護者支援や面談も、あれやこれやと支援が拡充するのは良いけれど、複雑性が増す一方で先生方も大変です。もちろんそれがうまく回ればめちゃくちゃ良いけど、回ってないのならば、それは先生方に余力がない、余裕がないことが全てであろうと感じます。
主体性の評価の導入も、撤廃も、トップダウンの改訂に現場が振り回されている感は否めません。
足すより引いてもいいんじゃないかな。ただ引いたら混乱だけど。
そのために、私は教師の人数と、多様性も上がってほしいところです。
大学で教育学部を卒業してすぐ教師になった先生方には、見えないものがあるでしょう。社会経験の豊かな親と教師の間で起こってしまうなんだかよくわからないすれ違いはそれが一因かもしれません。「学校と教師と保護者は子供を支えるチームである」と、そんな言葉も聞きますけれども、「これまでの教育体系に順応してきた教師」が「順応しづらい子供」に下す評価が子供のその後の進路に直接影響を及ぼす以上、学校側がどうしても強くなることは否めません。
そして多様性を上げることで、尊敬される先生という教師像を取り戻すことにもつながってほしいと思います。
昔は、どれくらい昔かというと高等教育への進学率がそれほど高くなかった時代には、例えば大学に進んだ・卒業したという学歴自体がとても神聖なものでした。学力を中心に評価された大学入試下では、すなわち大学進学率が20%とかだった時代の教師は社会の中でも学力が上位20%の大人だったわけです。当時の教師は文句なしに“学業に優れた大人”であり、それはきっと当人にも大きな誇りであったでしょう。
かつてはその地域でも文句なしに尊敬される力のある人が教師になっていたからこそ、多様な子供を包摂し得ていたという側面はきっとあると思います。
それがどうやら、学力だけで大学入試が決まるのはアンフェアだという人の声が大きくなって(←なにが不公平なのか私には全くわかりませんが)、大学でも多様な入試形態が取られました。親の熱意と経済力に支えられた子供時代の実績を元手に大学入試は戦えたりして、そもそも今は大学だって選ばなければ全入です。今では、学校内の子供よりも基礎学力が低い大人が教師になってる地方もある。授業の質が低いとか、先生が辞書の使い方を子供に教えていないとか、そういう話もチラチラ聞くと腕を組まされるばかりです。

私のような理系博士の活用も、いいとは思う。しかし博士は教育を志して博士になっているわけではないから、教育のやり甲斐をどう博士たちに伝えるかがなかなか大きな関門です。私もそんな一人でした。だけどやってみるととても面白い仕事だなと感じています✨また、教育現場において博士人材を活用しようと思うならば、絶対的な枠組み調整は必要だとも感じていますが、それはまた機会があった時に。
多様な生き方をしてきた自己肯定感の高い大人が教壇に立つことに意義があると思います。
あれですね、メディアやSNSにおいて、教師がひどく負荷のかかる仕事であることが過剰なほどに、そして面白おかしく発信されたことは悪手だったんだろうと思います。先生になろうとする若者や成り手の絶対数が少なくなってしまいました。サラリーマン教師という言葉が言われ、学校と教師への社会の目もすっかり変わってしまいました。
今少し、力のある先生に裁量を持ってほしいなと思います。そのままの子供たちを面白がれる大人である人。誰か大人が心からその子を認めさえすれば、子供は素直に喜ぶのに。そうであれば、公教育はもっともっと引き算で構わないのかもしれません。
ーーー書籍紹介ーーー
📢【公式LINE限定オンラインイベントのご紹介📍 Zoom開催】
直近の開催は、 2025年9月12日(金)21:00〜(約1時間) を予定します。
テーマ:「高IQ児の受験あれこれ」
夏休みを終え、受験を控えるご家庭では本腰が入った?まだ入らない?笑。
高IQ児の受験に関わるエピソードを共有しあって、笑いと親の達観へ成仏させるところまでが狙いです。ご関心がある方は、現在公式LINEからご案内中です。

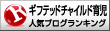









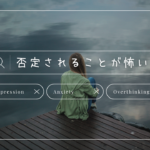
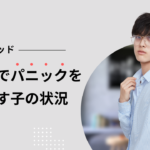
コメント